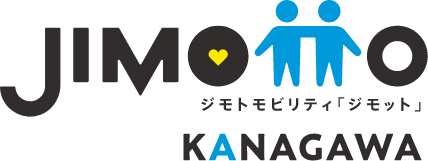[ 社会福祉事業 ]
社会をやさしくする
このまちの人々が大切にしてきたCare(ケア)を基盤に、
他者を思いやる心を育み、福祉をひろげ、優しい社会を築きます。



理事長
馬場 拓也さん
「社会福祉は、電気・ガス・水道と同じインフラ」。そう語るのは、神奈川県愛川町で社会福祉事業を展開する社会福祉法人愛川舜寿会の理事長、馬場拓也さんです。高級ファッションブランド出身という異色の経歴を持つ馬場さんが、なぜ福祉の世界に飛び込んだのか。そして今、どんな社会福祉のかたちを目指しているのか。2022年、地域共生文化の拠点として生まれた「春日台センターセンター」で、その想いをうかがいました。
"この世界には可能性がある"
──盆踊りが変えた人生
社会福祉事業に関わるきっかけは、2007年、31歳のときに地元で手伝った盆踊りでした。両親が運営する特別養護老人ホーム「ミノワホーム」で開催されたもので、帰省のタイミングで久しぶりに参加しました。
私は15歳で地元を離れ、山梨県の高校で寮生活を送り、その後、千葉の大学を経て、東京のアパレル会社に就職しました。当時はITバブルや外資系ブランドが勢いづいていた時代。いわば資本主義のど真ん中で働いていましたが、どこかで「この世界がずっと続くとは思えない」と感じていました。 そんななかで起きたのが、2008年のリーマンショックです。経済が大きく揺らぎ、アパレル業界を含む社会全体が冷え込んでいきました。ミノワホームの盆踊りに参加したのは、その頃のことです。
祭りの場で目にしたのは、車椅子の方や障害のある方、外国人、地域の高齢者や子どもたちが浴衣を着て、やぐらを囲んで盆踊りを楽しむ姿でした。多様な人びとが集まっているのにも関わらず、不思議な調和を感じました。
「この世界には何か可能性がある」。その光景を見たとき、強くそう感じました。


"助ける"から"共に生きる"へ
──対等なケアをめざして
それをきっかけに地元へ戻り、福祉の現場で働き始めたのですが、最初は、施設内の壁に手書きのチラシがたくさん貼られていたりして、あちこちが"ガチャガチャしている"と感じていました。
主催した盆踊りでは、地域の小・中学校や企業から借りてきた、学校名や社名入りのパイプテントがずらりと並びました。ブランドイメージの統一や一貫性が重視されるアパレルの世界にいた私は、「ロゴを揃えて、ミノワホームの祭りとして統一したほうが見栄えがいい」と考え、施設長である母に提案しました。 すると母から返ってきたのは、「あなた、分かってないね」というひと言でした。「いろんな学校や企業の名前が見えることで、地域とのつながりが目に見えるかたちになっている。それがいいのよ」と。
その言葉に、はっとさせられました。ごちゃごちゃしているように見えた風景のなかに、地域との関係性がしっかりと表現されていたのです。見た目の整え方ばかりに目を向けて、混ざり合いの意味に気づけていなかったんですね。 この経験は、自分の価値観を大きく揺さぶりました。福祉の現場で本当に大切なのは、いろんな人が自然に関わり合えることなんだと、気づかされました。

福祉はインフラ
──支える・支えられるを越える
福祉は電気・ガス・水道と同じように、暮らしを支えるために欠かせない存在──つまり「社会的インフラ」だと考えています。
たとえば、今は女性が社会で活躍するのが当たり前の時代ですが、妊娠・出産・子育ての場面では、子育て支援や児童福祉の支えが欠かせません。また、親が倒れたときには、高齢者福祉が必要になる。人生のさまざまな局面で、福祉は日常と切り離せない基盤として存在しています。
日本の福祉は戦後、いわば「弱者救済」というかたちで成り立っています。そのため、「裕福な人が、恵まれない人を助ける」という意識が、今もなお根強く残っています。だから福祉の「お世話になる」ような気持ちが強かったのです。しかしこれからの人口減少社会では、「支える・支えられる」といった非対称の関係ではなく、社会基盤として「共に生きる」という対等な関係性へと転換していく必要があると感じています。
そのためには、福祉を受ける人にも、ほんの小さな役割を担ってもらうことが大切です。そうすることで、その人の存在価値や自信が自然と育ち、対等な関係をつくる第一歩になります。
たとえば、食事の場面でも、「どうぞ召し上がってください」と一方的に提供するのではなく、「○○さん、このテーブルの人たちにお茶を配ってもらえますか?」とお願いする。そうした日常の小さな関わりの積み重ねが、自立や誇りにつながっていきます。
介護は決して"おもてなし"ではありません。その人が"自分らしく生きられる"ことを支援する。それが、私たちが目指しているケアのかたちです。




"共に生きる福祉"をかたちに
──春日台センターの再生
こうした「対等な関係性」や「共に生きる」福祉を、どんなふうに表現できるのか──そのひとつの答えが、私たちが取り組んだ「春日台センター」の再生プロジェクトです。
愛川町にはかつて「春日台センター」というスーパーがありました。コンビニもなかった当時、酒店や模型屋、駄菓子屋などの個人商店が並び、私の幼少期である1980年代頃、春日台センターはまさに地域の中心でした。 そのスーパーが2016年に閉店すると聞き、放っておけないと感じました。みんなの思い出の詰まった場所を、もう一度人が集まる場所にする。「春日台センターセンター」という名前には、「春日台センターをもう一度このまちの中心(センター)に」という意思を込めています。
春日台センターセンターは、多様な機能を持つ複合施設です。障害者に就労の場を提供する「春日台コロッケ」や「洗濯文化研究所(ランドリー)」、障害のある子どもたちが放課後に通う「カスガダイ凸凹文化教室」、高齢者福祉の場である「KCCグループホーム」や「KCCショータキ」、さらに地域の子どもたちが学ぶ寺子屋や、住民の憩いの場となるコモンズルームも備えています。これらの機能は、地域の人たちとワークショップを重ねながら、「この場所に何が必要か」を共に話し合い、見つけてきたものです。
建築にもこだわっています。そのひとつが"あえて便利すぎないこと"。便利すぎると人の基本動作や自立の機会や助け合いの場面を結果的に奪ってしまうこともあるからです。
たとえば、自動ドアではなく手動のドアを採用したのは、「自分の手で開け閉めする」という動作を残すためです。また段差を設けることで、「お手伝いしましょうか」と声をかけるきっかけが生まれ、自然な気づかいや人との関係が育まれるように工夫しています。


"ハレ"より"ケ"
──日常の中で孤立・孤独対策を
人や地域とのつながりといえば、盆踊りやイベントのような"ハレの日"を思い浮かべる人が多いかもしれません。でも、私が本当に大切だと思うのは、"ケの日"──つまり、なんでもない日常です。
春日台センターセンターには、施設のあちこちに座る場所があります。そのひとつ、高齢者が過ごす場の窓辺のベンチには、いつもひとりでゲームをしている男の子が座っています。彼は友達の輪に積極的に入るタイプではありません。でも背後には、おじいちゃんおばあちゃんの話し声、テレビやキッチンの音が漂っている。そんな環境に"なんとなくいる"だけで、彼にとっては安心できる、十分に意味のある居場所になっているのです。
今の社会は価値観が多様化し、変化のスピードにも人の感覚が追いつけていないように感じます。その結果、こぼれ落ちる人が増えている。私たちは「ちょっと浮いてしまった人たちがアクセスできる場所」をつくることが大切だと考えています。 効率性ばかりを追うと、大切なものが置き去りになってしまう。非効率の中にこそ、地域の人や子どもたちと自然につながれる場が生まれます。誰にも声をかけられずに、ただ静かに座っていられるベンチ。お金がなくても、気軽に立ち寄れるスペース。そうした"余白"があるからこそ、人はまたその場に戻ってこられるのだと思います。
「これは施設として本当に必要か?」と問われたとき、「なくても困らないけど、あったら嬉しい」ものを、どれだけ真剣につくれるか。それが僕らの仕事の本質なんじゃないかと思っています。"ロマン(理念)"と"そろばん(採算性)"、そのバランスをどう取るか ── そんなことを、いつも考えています。


「なくても困らないけれど、あったら嬉しい」
── その余白こそが、人と人を結ぶ力になる。
効率や合理性だけでは測れない価値を、愛川舜寿会は日常の中に丁寧に積み重ねてきた。
小さなつながりがやがて地域を支える大きな力となる。
その信念を胸に、同法人、そして馬場さんたちの挑戦は、普段着の福祉のあり方を静かに、しかし確かに形にし続けている。